読売オンラインより(青字化、リンク追加筆者)
高線量報じる難しさ
当初行政の測定なし/データ本紙初掲載は5月
東日本大震災の発生後、読売新聞千葉支局は総動員で、被災現場や行政の取材に当たった。東葛地域では東京電力福島第一原子力発電所事故により、高い放射線量が観測されたが、当初は情報が不足し、どこまで書くか難しい判断に迫られた。放射線問題をどう報じたか、検証する。
◇
昨年4月下旬、「東葛地域の放射線量が高いらしいが大丈夫か」という読者からの問い合わせが寄せられるようになった。根拠の不明確な話が多かったが、取材の結果、出所は東大のホームページだと分かった。
東大が公開していた柏キャンパスの空間放射線量(地上1メートル)は、3月21日に毎時0・80マイクロ・シーベルトに達していた。後に国が定めた除染基準の毎時0・23マイクロ・シーベルト以上(同)よりは高いが、原発事故との関係が不明確で、紙面化は見送った。
市民や研究者が測定した線量をインターネットで発信し始めると、住民に不安が広がった。本紙は県や市に取材したが、行政は東葛地域で測定しておらず、情報はなかった。
こうした中、本紙5月16日付朝刊「震災掲示板」に、「チェーンメールで放射線のデマ拡大」との記事が載った。文部科学省の指摘などを引用し、柏 市などで放射線量が高いといううわさは根拠がないとして警鐘を鳴らす内容だった。ただ、デマと決めつけられる根拠は乏しかった。
千葉支局が東葛地域の放射線量を初めて報じたのは、自治体の先頭を切って松戸市が独自に測定した結果を掲載した5月26日付朝刊「東葛版」だった。
ほかの市や県も測定を始めたが、大半は子供の屋外活動を制限する国の基準(毎時3・8マイクロ・シーベルト)を下回った。このため、7月7日付朝刊県版で報じた「放射線量 全県で基準以下」などでは、専門家の談話も交え、不安をあおりすぎないよう配慮した。
東葛地域の放射線問題を更に大きく取り上げたのは、7月、柏市などのごみ処理施設の焼却灰から高濃度の放射性物質が検出された後のことになる。
◇
火災や液状化、津波被害は、当局の発表が足りなくても、記者が現場で見聞きした内容を原稿に反映できる。しかし、放射線は目には見えないし、臭いもしない。現場を歩いても、書ける情報はなかった。
住民らが計測した数値はあったが、測定時の環境や機器の精度によって結果は違ってくるため、無条件に掲載はできない。行政の発表を待つことにした のは、低線量被曝(ひばく)は比較的リスクが低いことを考慮した結果だが、リスクについて専門家の間でも見解が分かれる中、ニュースの価値判断が難しかっ たという面も否めない。
当局も情報を持たず、記者が現場に足を運んでも事実を確認しづらいという非常時は、またいつ訪れるか分からない。それに備え、日頃から様々な知識 の吸収に努め、臨機応変にあらゆる角度から取材を尽くせるよう、修練しておく必要性があると痛感した。
(倉茂由美子、淵上隆悠)
(おわり)
(2012年3月11日 読売新聞)
---------------------------------------------------------------------------
日刊サイゾーより(青字化筆者)
NHK『ネットワークでつくる放射能汚染地図』いま明かされる舞台裏
震災から2カ月を経た昨年5月15日、Twitterを中心に、NHKで放送されたある番組が話題となった。ETV特集『ネットワークでつくる放射能汚染地図~福島原発事故から2
か月~』。元理化学研究所の岡野眞治博士や元独立行政法人労働安全衛生総合研究所の研究官・木村真三博士らの全面的な協力の下、福島県内の2,000キロ に及ぶ道路を測定したこの番組。専門家と共に調査された詳細なデータから、福島で進行する放射能汚染の現状を紹介した。この番組によって、ホットスポット として知られる浪江町赤宇木地区の現状が映し出され、政府の指定した緊急時避難準備区域である30キロ圏の外側も、必ずしも安全ではないという事実を教えた。
文化庁芸術祭賞、早稲田ジャーナリズム大賞、日本ジャーナリスト会議大賞など、数々の賞を贈られたこの番組はシリーズ化され、現在までに『海の ホットスポットを追う』『子どもたちを被ばくから守るために』などを放映。震災から1年となる2012年3月11日にはシリーズ5作目として『埋もれた初 期被ばくを追え』と題した弘前大学による事故初期の甲状腺調査や、気象シミュレーションによる各地のヨウ素131の濃度が紹介される。
そして、この番組の制作者たちの手記が集められた『ホットスポット ネットワークでつくる放射能汚染地図』(NHK ETV特集取材班・講談社刊)が刊行された。これは、原発事故の真実を追いかけたドキュメンタリーの裏側を明かす1冊である。
番組制作の中心を担ったのはディレクターの七沢潔氏。『チェルノブイリ・隠された事故報告』『放射能 食糧汚染~チェルノブイリ事故・2年目の 秋~』『原発立地はこうして進む 奥能登・土地攻防戦』など、原子力に関連した良質なテレビドキュメンタリーをつくってきた人物として知られている。しか し、東海村JOC臨海事故を取材した『東海村 臨界事故への道』を制作直後、放送文化研究所に異動。その後は番組制作の現場から遠ざかってしまった。国内 の原子力問題を追求したことが仇となり、閑職へ追いやられてしまったのだ。
だが、福島第一原発事故は七沢を必要とした。原発を特集したドキュメンタリーを企画した大森淳郎チーフディレクターは、七沢の携帯電話を鳴らす。「やっぱりあんたに来てもらいたい」。
この番組でスタッフと共に、各地の詳細な放射線量を計測した木村博士もまたリスクを背負って参加をした人物だ。厚生労働省が所轄する労働安全衛生 総合研究所研究員だった当時、「パニックを防ぐ」という名目で、同所には厳しい研究規制が敷かれていた。「行動は本省並びに研究所の指示に従うこと。勝手 な行動は慎んでください」そのメールを受け取り、彼は辞表を書いた。翌日、番組の打ち合わせに出席し、彼は七沢らと共に福島へ向かう車に乗り込んだ。
今年86歳を迎える岡野博士にとって、長距離の移動だけでも体力的には無理がある。さらに、低血糖症であるため、1時間に1度ブドウ糖を補給しな ければ身体がまったく動かなくなってしまうという症状を抱えていた。しかし、岡野博士もまた、妻の郁子さんと共に現地取材班に合流し、福島で彼オリジナル の測定器を操った。
ほかのスタッフたちにもさまざまな物語がある。放射線を浴びるかもしれないという危険だけでなく、それぞれがリスクを抱えていたのだ。
なぜ、彼らはそのようなリスクを背負ってまで福島に向かったのか。七沢は、それまでの原発取材の経験からこのように記している。「原発と、それを 押し進める巨大な体制に根こそぎにされ、人生を奪われた人々を取材するにつけ、その行き場のない怒りと悲しみを知り、解決できない現実から逃れることがで きなくなった」
放送後、苦労の甲斐あって番組は高く評価された。しかし制作当時、この番組はNHK局内から冷ややかな視線が送られていたという。局内のルールと して30キロ圏内での取材が規制されていたにもかかわらず、彼らはその規則を破った。番組内容を聞きつけた上層部は「偏向しているのではないか」と危惧 し、当初4月3日の放送を予定していた番組は5月に延期された。チーフプロデューサーの増田秀樹は「放送ができなかったら切腹では済まされない」と思いつめた。この番組の評価を考えれば、今では考えられないことばかりだ。
しかし、彼らは番組を制作し、社会に対して大きなインパクトを与えた。放送終了後、電話やメールなどで1,000件以上の再放送希望が寄せられ、NHKオンデマンドでは大河ドラマを凌ぐリクエストが集中した。
増田は、本書にこう寄せる。
「私たちは報道機関の端くれとして『事実を取材して伝える』という当たり前の仕事を、当たり前にやっただけで何も特別なことはしていない。山奥に置き忘れられていた非常用電源のようなもので、たまたま水没を免れ稼働を続けたに過ぎなかった」
この“非常用電源”が機能していなかったならば、福島第一原発と同様、メディアもまた暴走を続けてしまっていたかもしれない。『ネットワークでつくる放射能汚染地図』という番組は、日本にもまだ信頼できるメディアが存在しており、正しい情報を与えてくれるということを人々に確認させてくれた。
七沢はあとがきに記す。
「この本では通常の番組本では書かれない機微な舞台裏も描かれている。それはNHKという組織内の状況も含め、番組が制作され、放送にまで至った プロセスを描かなければ、原発事故直後、日本中が『金縛り』にあったかのような精神状況、メディア状況下で作られた番組のメイキングドキュメントにはならない。(中略)有事になると、組織に生きる人々が思考停止となり間違いを犯すことも含めて描かなければ、後世に残す3.11の記録とはならないと考えたのである」
(文=萩原雄太[かもめマシーン])
●ETV特集『ネットワークでつくる放射能汚染地図5 埋もれた初期被ばくを追え』
3月11日(日)夜10時~
<http://www.nhk.or.jp/etv21c/file/2012/0311.html>
ホットスポット ネットワークでつくる放射能汚染地図
NHKの底力。
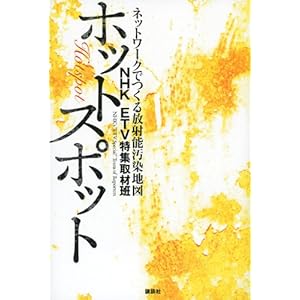
0 件のコメント:
コメントを投稿